

巻頭言: KEYNOTE ADDRESS
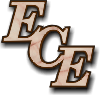
応用生態工学とは何か,
それは今後どのように進めていくべきか1)*
川那部 浩哉
応用生態学研究会会長, 琵琶湖博物館館長, 京都大学名誉教授〒525-0011 草津市下物町 2) President of Ecology and Civil Engineering Society,
Director General of Lake Biwa Museum, Oroshimo, Kusatsu, Shiga 525-0001, Japan
発足まで
「応用生態工学会ないし研究会を作りたい」. このような話が, 河川の土木工学関係者の側から, 私のところにまで持ち込まれた最初は, たしか1995年の冬であったと記憶する.河川ないし湖沼における土木事業に関連する生態学的な仕事には, 大学院へ入学してすぐからいくらか携わらされて来ていたし, 1957年からは非公式に発言し, 1960年代前半からはいくつか書く機会もあった. だが当時は一般に, 生態学的な立場からの要請が, 河川事業の関係者にとにかく聞いて貰えると言う機会すら, まことに稀有だったように思う. すなわち,「自然環境の保全など考慮の余地なし」と, 一笑に付されるだけの時代が続いた. いやそれどころか, 「川那部とだけは, 絶対に口もきかない」とのたまう関係高官(複数)もあったと嘘か本当かは知らぬが, 何度か仄聞したものである. そのうち「治水・利水に影響のない範囲でいくらか考慮してもよい」との話が出始め, 最近になって「自然環境への影響にも配慮しつつ, 治水・利水の目的を達成する」となった. そして1995年に「河川審議会」がやっと, 河川行政の目的を「治水,利水,自然環境の保全」の3つだとし, その結果「河川法」が改正されるに至るわけである. こうして, 総論についてはときに意見の一致するかに見える出来ごとが, この頃, 少しは存在するようになって来た. したがって, 河川工学の研究者あるいは技術者と生態学の研究者との率直で地道な議論が, 従来のような非公式な, 言わば友だちどうしのあいだだけではなく, 比較的開かれたところで行ない得る状態になって来たのではあるまいかと, 私自身も気にし始めていた, その矢先のことであった. 最初の発言を大いに歓迎しながらも, 取り敢えずは生返事をしてきたものである.
それが1997年初頭から話が急に動き始め, 近い将来の学会への移行を見越しつつ, 取り敢えず研究会として, その秋に発足させたいとの意向が表明された. それならばと私は, 自由な交流の場となることを前提に, 発起人の1人になることを承諾した. 時あたかも7月15日には, 廣瀬利雄さんの監修, 応用生態工学序説編集委員会の編集になる, 『応用生態工学序説−生態学と土木工学の融合を目指して−』が出版された.
この本については, 私としては珍しく早く, 8月5日に書評を脱稿し, それは廣瀬さんのお骨折りで, 日本河川協会の雑誌『河川』の9月号に載った. 掲載誌を読んで貰えば判ることだが, 生態学の側の研究者には, この雑誌を見るのは困難かも知れないので, その一部を, ここで繰り返しておきたい.
「<応用生態工学>のめざすところは, 端的にいえば生態学的知見を土木工学の分野に応用することにある」とか, あるいは「<応用生態工学は技術論である>ことを明確にしたい」と言う, この本の主張に対して, 私は先ず, 全体的に異論を述べた. それはこうだ. 「せっかく生態学と土木工学が互いに手を差し伸べて, 境界領域をともに考え実行して行こうとするのならば, それによって, 生態学のほうにも新しい領域が作り上げられ, あるいは, 生態学自身にもある種の変更が起こり得る, そのような契機となる可能性が 考えられるべきではないのか. そう言う相互浸透性が, どうしても必要だろう」とし, また,「価値論から独立の技術論とは, 立言者の意図のいかんにかかわらず, 特定の価値観を, あるいはいくらか広くとも, ある特定の価値観群を前提とする, そう言う<技術論>に他ならない」, と言うのがそれである.
だがこの本には,「当方が忸怩とするような発言」もあった. すなわち「<土木工学者は,過去においては,魚の問題が生ずれば魚の学識者に, 鳥の問題が生ずれば鳥の学識者にだけ指導を仰げば, 問題を解決できると考えてきた. しかし,生態系は,各種の生物が複雑に関連し, 影響しあって成立しているものである. したがって, 応用生態工学は生物学の複数の部門と土木工学とが, 一つの場で総合的に論議すべきものである>」, とするのがそれだ. これには,「生態学研究者は, これを読んで, いささかならず恥ずべぎではないだろうか. 生態学は, 確かに特定の生物種ないし生物群を対象ともするが, 一方では<複雑に関連し,影響しあって成立している>群集をも対象としている筈 だからだ. <群集生態学研究者は, 少なくとも日本には存在しない>と言われているに等しいと理解し, 大いに反省して, これに何らかの反応をすべきではあるまいか」, としておいた.
そして, この書評の結論はこうである.「応用生態工学は,今から模索しながら作り上げて行くべきものだ. この本に書かれているのは, 生態学と土木工学とを何とか対話させようとし, そのために努力を重ねてきた, 数少ない土木工学の実際家の一人, 廣瀬利雄さんが監修し, そして, それに賛同し, またある程度実際に動いてきた編集委員会の人々の作り上げた, まさに先駆的なものである. しかし, これは当然ながら, 応用生態工学に関する, 1つの意見に過ぎない. その内容においても, 重要な問題で, ここには触れられていないものも数多い. 数ならぬ身の私にも, この本の<基礎編>に書かれていること自体に, いや, 目標についてすら, 先に述べたとおり, 大いなる異論がある. 先駆的な出版物は, 批判され, 乗り越えられるために, 存在すると言っても過言ではない. 応用生態工学を今から作り上げるためにも, 読者はこれを読んで, 全面的に論議を始めて貰いたい. それがこの, 野心的な本に対する礼儀でもある」.
この書評がやや感傷的なのは, 上記のような歴史,いや「自分史」をも踏まえて, いささか感無量であったためでもある. そして, この本に対する異論を, 敢えて鮮明にしたのは, 応用土態工学研究会の発足にあたって, この研究会は, これから自由に議論を始める場であり, 間違っても出発の時点から, ある考えに基づいてのみ作られるものではないことを, 内外に明示しておきたかったからでもある.
哲学の革命期における科学技術
地球環境問題が最大の課題になっている現在, 科学哲学の, いや, 一般市民の哲学においても, 全面的な変化が明確化してきている. これは, 19世紀中葉の進化論革命, 20世紀初頭の量子力学革命に匹敵する, あるいはそれを越える変化を科学技術全般にもたらすものである. その口火を切ったのは, 今になってその先見性は一層はっきりするのだが, R.カーソンさんの『沈黙の春』だったようだ. 私は1996年頃から, 何回かこの話をしているが, 応用生態工学と言う新しい境界領域を作りげようとするこの会の発足にあたっても, そのことを繰り返し確認しておきたい. それは,3つないし4つの変化として捉えられる.
第1は, 私たちの棲んでいる地球が, 明らかに閉鎖系だとの認識である. 「開放系」と見放し得た時代には, 例えば廃棄物濃度を薄めて, 遠くへ拡散させれば良いと考えることが出来た. しかしそれが不可能なことは, 今や明らかになった. 総量以外は考えられない, 「元に戻す」 こと以外に真の解決のないことが, 明白になったと言ってもよい.
第2は, ものごとは私たちの想像以上に, 深く絡まり合っているとの認識である. 農薬や殺虫剤が「思いがけないところにまで」 影響を及ぼすことは, 初期からの「見易い」事例だったが, 生物と生物あるいはそれに非生物環境が絡まった総体がいかに複雑なものであるかは, 調べれば調べるほど, いや今や目の前で起こっている自然の変化を少し詳しく凝視するだけでも, 心に納得できる様相を呈してきている.
第3は, 実は第2のものの系なのだが, 科学ないし技術の発達は, まだまだ不完全であり, 少なくとも当分のあいだは, 自然の極く一部をしか解明しあるいは解決し得ないものであると, 明白になって来たことである. いわゆる単純な「公害問題」において, その個々の解決に果たした日本の科学技術の役割は, 評価する人がかなり多いと聞き及ぶ. しかし部分の最適解の集合は全体の最適解たり得るか. これについては, まだ何も判らないのだ. また科学・技術の細分化がこの状況を生むのに拍車をかけてきたのであり, 従ってそれを打破する必要のあることも, すでに明らかになってきた.
第4は, 時間軸に添って起こる変化すなわち歴史性なるものが予想以上に重要らしいことの, 改めて明らかになったことである. 科学ないし技術は従来, できるだけ時間概念を無視して解析を進めようとしてきた. しかし現在の地球環境問題は, 40億年をかけて営々と築き上げてきた地球の歴史の中で, 考えかつ対処しなげればならないことである.
1995年初頭に出された総理大臣の私的諮問機関「21世紀地球懇話会」の報告が,「循環」と「共生」をうたい文句にしていることも, まさにこの第1と第2の「哲学」の変化に対応しているのだ.
ついでに言うと, 1992年にリオ・デ・ジャネイロで開かれたいわゆる「地球サミット」では, 行動指針として「アジェンダ21」も発表された. その第18章は「淡水資源の質と供給の保護:水資源の開発,管理及び利用への統合的アプローチの適用」で, その序文の最初は次の通りだ(この公式の翻訳には, 気に入らないところが多いのだが, ここでは我慢してそのまま引く). 「淡水資源は地球の水圏の必須の構成部分であり, 地上のすべての生態系の不可欠の部分である. 淡水環境は水文循環によって特長づけられる. (中略)水は生命のすべての側面において必要とされる. この章の全般的目的は, この惑星の全住民に良質の氷の充分な供給を維持し, その一方で, 生態系の本文, 生物, 化学的機能を保存し, 人間活動を自然の容量限界内で適応させ, かつ氷に関係する疾病のベクトルと闘うことである」. そうなのだ. 「水資源の開発,管理及び利用」のための「アプローチ」とは,こう言うものなのである. 繰り返すまでもないだろうが, 「水環境の悪化や生態系への影響にも配慮しつつ, 資源開発を行なう」などと言うのとは, 全くなったものであることに, 注意すべきである.
さて, 「地球サミット」の主題が, 「持続的開発」だったことは周知のところだ. ところでこの「持続的開発」だが, サステイナブル=デヴェロプメントの訳としては, 意識的か無意識的かは知らず, 誤訳だとの噂が巷にはあると聞く.
サステイナブルとは, もともとは「耐え得る」の意味だそうだし, 「批判に対して弁護し得る」との意味は, もちろん今も生きている. 『オクスフォード新英語辞典』の「本体」には, この2つの意味しか出ていない. 1986年に出た「補遺」で初めて, 「一定の率・水準に保ち得る」の意味が載る. ある『経済学辞典』が1965年に, 「サステイナブルな成長」と使ったのが, この意味の初出だそうだ. ついで, 「クジラのサステイナブルな漁獲」(1971), 「サステイナブルつまり増減しない人口」(1976), なる例が出ている. サステインと言う動詞は,「価値や正当性を擁護する」,「失敗したり落ち込んだりしないように支持する」, 「正しい立場を保持させる」の意だから, これは当然だろう. デヴェロプメントも,「折り畳んだものをゆっくり拡げて,くまなく見せる過程」が本義だ. そこで「閉じ込められたものを, 本来の姿に展開させる過程」,「段階を追っでゆっくりと進行する過程,あるいはその結果」となる. 同じく『オクスフォード新英語辞典』の「補遺」で初めて,「潜在的なもの(例えば鉱山・用地・資産)を実現させる過程」との意味が出てくる. 但しこのほうには, 古く1885年からの用例がある.
つまりサステイナブル=デプェロプメントとは,「正しい状態を保たせ,ゆっくり展開させて行くこと」との意味なのだ. 少なくとも, 日本の現状がいっそう開発され, 経済的に増大し続げて行くなどと言うのは, この範疇には入るまい.
では, 地球規模ではどうか. エネルギー消費だけを見ても,「南」の国々のそれは, まさに飛躍的に増加している. これが「北」の国々の現在享受している基準に達すれば, 全体として地球を破滅させるに充分である. 1987年の1人あたりエネルギー消費量は, バングラディッシュを1とすると, 日本で110, 合州国で280だと, アメリカ統計局が報じている. すなわち, 少なくとも先進国にとっては, エネルギー消費を, 現在の状態から格段に切り下げることが, どうしても必要なのだ.
自然現象における歴史性
さて, 例えば河川工学においては,「何十年確率の洪水」などと常に言う. いやそれを基礎にして, ダムなどが作られてきた. したがって時間の概念は, その考えの根底に充分に入っている筈だと思うのだが, 意外にそうではないらしい. 上記のこと以外では, 相も変わらず平均値(と標準偏差)が, まかり通っている. 一例を挙げよう. これは1970〜71年に『公害と対策』なる雑誌に連載し, ただし未完のままになっている「河川水域の生態学的考察」の一つにも書いたことだが, それは次のようなことである.
あるダム建設にあたって, アユ漁業のために下流への放流水量が決められた. 仮に毎秒5トンだったとしよう. 完成後, それが守られていないのではないかとの話があって, 見に出かけた. 管理所長の話は,「夜の12時間は10トン, 昼の12時間は0トン, すなわち一日平均5トンの放流で, 決定どおり」とのことであった. いささか呆れた私は,「24時間のうち10分だけ, 空気中の酸素を0にすると人間はどうなるか」と聞うた. 所長は,本当に始めて気付いたらしい. 直ちにこのような放流は中止され, その後は最低流量として, つねに5トンが確保されたと聞く.
姫川の平水流量と河床の石の状態とは, 明白にバランスを失している. あれはむしろ, 洪水流量に対応しているものである. それは当然のことで, あの河床は洪水時の流れによって, 主に作られて来ているからだ. そのことを充分に理解している筈の人々が, 極めて短時間であろうとも, 極端な条件によって生物が消え失せることが理解できないのは, それこそ私には理解が出来ない.
「人工的な変化によって, 生物が得をする面もあるのではないか. ダム湖が増えて,喜ぶ生物は本当にないのか」, このように尋ねられたことも数多い. 実はある. 古くから知られている例で言えば, 例えばオイカワは, ダム湖の出現によって, その上流部で個体数を増すことが多いと, 1950年代後半に水野信彦さんと名越誠さんが報告している. だが, 1つの種の著しい個体数増加は一般的に, 全体に及ぼす悪影響が著しい.
近年いつも使う例で, 生態学の関係者には耳にたこが出来ているだろうが, ここは土木正学関係者への説明だと思って, もう一度我慢して欲しい. それは, 高林純爾さんたちの「3体問題の化学生態学的研究」である.
一般に植物は, 植食動物に食われないために, さまざまな対抗手段を作り上げてきた. 陸上植物がセルローズを中心とする硬い組織を作り上げたのは, 被食から己の体を守る重要な手段の1つにもなった. それと同時に何らかの忌避物質を分泌することによって, 植食動物その他からの攻撃に対抗することも, 古くから知られていた. 動物は動物で逆にこの忌避物質に反応せず, あるいはその毒性を小さくするような解毒物質を作る手段で抵抗した. したがって植物は, さらにこれに対抗する必要を生じる. 植食動物の中には, この植物の作った毒を体内に溜め込み, 自分を食いに来る肉食動物に対する毒として, これを「有効利用」せんとするものも生じた. フグ毒たるテトロドトキシンもまた, フグ自身が作ったものではなく, 細菌によって作られたものに他ならない.
これとは別に, 例えば葉とそれを食うダニや昆虫とそれを食う肉食性のダニや昆虫の, 3者のあいだなどで, 次のような関係の存在することが近年明かになってきた. 例えば植食性のハダニがこの葉を食う. そうすると葉は, ある化学物質を分泌する. この物質は, このハダニに対する直接の対抗物質ではなくて, そのハダニを食う捕食のダニを呼び寄せる, 言わば「泣き声物質」なのだ. これを嗅ぎ付げて捕食性のダニが現れ, ハダニを食うというわげである. この物質は詳しく同定されているが, 人間が葉に傷をつげたと言った状態では分泌されず, したがって捕食性のダニを呼び寄せる効果はない. これはあたりまえで, 傷ついただげでこの物質が出れば, それに呼び寄せられた捕食性のダニは, 「くたびれ儲け」になるだけで, 葉は「狼少年」以外の何ものでもなくなる. ハダニにはいくつもの種があり, 種によってそれを捕食するダニの種も異なるので, 葉を食うハダニの種に応じて, 異なった「泣き声物質」(正しくは, いくつかの成分の比率の異なる物質)が分泌されるのである.
これは明かに, 3種の関係が存在することによって成立した物質であり, それを作り上げる葉の性質である. また, そのような関係が現在まで続いているからこそ, 言わば「費用」をかけても持続している葉の性質である. さまざまな植食動物がいるからこそ, それぞれを攻撃する捕食性の動物を呼び寄せるべく, さまざまな物質を分泌するための, さまざまな「遺伝子」を作り上げ, 残してきたわけである. それではどの程度の時間があれば, 生物は自然淘汰の結果として, このような遺伝子を確立するのか. この場合は良く判っていないが, バクテリアなどを除く通常の植物や動物の場合, はっきり異なる種が成立するためには, 最低4000年, 通常は数万年以上の時間のかかることは, 記憶しておいて良いことだろう. すなわち, 生物にとって重要な時間概念とは, 生命が絶たれる意味では本当の一瞬でそうなるのであり, いっぽう進化の意味では, 数万年が変化のための「一瞬」なのだ.
過去からずっとその関係の存在し続けていることが生物の性質を決めているとは, 逆に言えば, 過去に出会ったことのない生物どうしにおいては, 直ぐには関係は, 少なくとも適切な関係は, 結ばれないことを意味する. 外来種の導入が, 地球上のあらゆるところで大問題を起こしている所以は, ここにある.「歴史とは共有された時間である」との定義があるやに聞くが, 歴史の共有が, 関係の成立には不可欠なのだ.
思えば自然科学は, 出来るだけ時間概念を捨象するように努めてきた. 時間を考えに入れなければならない場合でも, 瞬間の累積として考えるべく努めてきたと言っても, 過言ではあるまい. しかし生物学的なものはもとより, 地球物理学的なものも地球化学的なものも, 自然界の現象は実はすべて長い時間の結果であり, いや,具体的なその場所ごとに時間を共有してきた, すなわち「歴史的」産物なのである. 前節で挙げた4つの変化のうち, まだ最も理解の不十分な第4のもの, すなわち, 時間軸に添って起こってきた変化の重要性は, 応用生態工学においてはいま特に, いくら強調しても強調し足りない程のものなのである.
自己の科学・技術の基盤を掘り崩し,危うくさせよう
「応用生態工学は, 今から模索しながら作り上げて行くべきものだ」. 廣瀬さん監修の『応用生態工学序説』への書評として, こう述べておいた. すなわち, 応用土態工学は, 生態学と工学との境界領域として, 今まさに出発しようとしているところである.
ここで, 具体的な言葉について率直に述べておきたい, それは, 「多自然型川づくり」なる用語のことである. 1997年9月16日に水資源開発公団で, 「生態系の概念について」なる講演, いや講義をしたことがある. 録音を起こしたものは, その直後に送って貰ったのだが, まだ直しが済んでおらず, なんとか1998年中には完成させたいものと思っている. それはともかく, 「生態系」と言うのは, 実はかなり錯雑した概念なので, 「言葉の大切さ, 原典にあたることの大切さ, に関する4題」を, 頭のところで話した. その第1は「インフォームド=コンセント」, 第2は「塩分・塩素量の定義」の問題だったが, その第3として挙げたのは, 「多自然型」である. 書き直したものを, 未定稿ながらそのまま転載しよう.
「この<多自然型>なる日本語は, ドイツ語の訳から来たのだと思うのですが, もしそうだとすれば, もとの語はく自然に近い( Natur nahe)>に違いありません. それではどうして, <近自然>ではなく<多自然>と, わざわざ<誤訳>したのでしょうか. ひょっとすると, <少しではなく, 多く自然の方向へ近付ける>と言うことだったのでしょうか. しかし私には, 先日発刊されました『にほんのかわ』なる雑誌でも話しておきましたように, そこからはどうしても, <自然よりもいっそう自然性を多くするように, 人間が作り上げること>との考え, 言わば人間の, もっとはっきり限定して言えば土木工学関係者の, 自然に対する傲慢さを如実に示す, まさに象徴的な用語であると思います. はっきり言えば, この用語が用いられているあいだ私は, <このような工法を一切信じないでおこう>と, 心に決めているぐらいなのです」.
このことは, 環境に手を付けるなど言う意味では全くない. いや, すでにあまりにもひどくしてしまったことへの反省として, 自然に手を貸すことは, 残念ながら今やどうしても必要である. ただ, 先ほどの「歴史」のところからも明かだと思うが, 人間は自然を作り上げることなぞ, 金輪際出来ない. そうではなくて, 「自然を作り上げることの出来るのは自然だけである」ことに深く思いを致し, かつ哲学の革命の第3で述べたことを強く考えることによって, もっと自然に謙虚に, すなわち, 今まで自分たちはあまりにも自然を粗末にしてきたから, 自然が自然を作り上げ易いように, 僅かにお手伝いをするのだと言うことを, 痛切に考えて実行すべきだと言うに過ぎない. しかもこの作業こそが, すなわち, 自然あるいは自然に近いものを, これから遠い方向へ動かすことではなくて, 自然から遠くなってしまったもの, 正しく言えば, 自分たちがそのように変えて来てしまったものを, 自然に近い方向へ自然が自分で動いていくために, いかなる助力をなすのが可能かを考え, それを実際に行なうために, 議論を進め, また事実として試みてみることが, もっとも具体的な作業になるのではないか. こう言う意味でである.
ところで一般に境界領域なるものは, その後, その領域が境界ではなくて自立する領域になる場合もあれば, いつまでも境界領域として留まる場合もある. 前者の場合は, 明かに境界の両側にある学問領域は, 少なくともその一部は解体して, 境界領域がそれに取って代わることになる. それでは, 境界領域が境界領域として留まる場合, それは双方の学問領域に何をもたらすか. 互いに知識を交換して, 各々の学問領域の基盤を, いっそう強固なものにするだけなのか.
実はそうではないところに, 境界領域を設定する本当の意味があるのではないだろうか. 元来科学なるものは, 過去を, さらに言えば自分の過去の仕事を否定することから始まり, その基盤を掘り崩し, 自らの科学の立地を危うくするためにこそ存在するものである. そうでなければ, 科学にはならない. 境界領域は, それを比較的容易なものにする. 私が先に, 「生態学のほうにも新しい領域が作り上げられ, あるいは, 生態学自身にもある種の変更が起こり得る, そのような契機となる可能性が考えられるぺきではないのか」と問うたのは, その意味である. すなわち, 応用生態工学の発展によって, 生態学全体に, せめて大穴ぐらいは開け, 生態学の基盤をむしろ危うくしたいのだ. そこからこそ次の, 新しい生態学が生まれるかも知れないからである. 生態学を, あるいは土木工学を解体するものとして, 応用生態工学は進んで行きたい. それが私の願いである.
私は元来, 科学と個人とをかなり厳密に区分してきた. 例えば長良川河口堰の問題に関しては, 最初のいわゆる「マンモス裁判」の証言台に立ち, その後も, 建設省あるいは水資源開発公団に対して意見を述べた. しかし, 多くの関係者が間違って判断したのとは正反対に, 河口堰そのものに対する私の意見は,一切述べなかった. ただ, 「大丈夫だ」などとの発言に対して,「その証拠はあるのか」,「論理的に成立しないではないか」と論じただけであった. すなわち, 専門研究者としての範囲内に限って, 論議を行なって来たわけである. 生態学の研究者としての私に, 他人が尋ねたときの答えはそうあるべきだと, 私は今も思っている.
ところでこの会は, 応用生態工学研究会である. すなわちここでの議論は, 土木工学の研究者あるいは生態学の研究者が, 互いに他の学問領域の専門家に対して質問し, 答える場ではない. この点, 先ほどの話とは全く違うことに留意せねばならない. すなわちこれからのこの研究会の中での議論は, 専門家集団間のものではなく, 専門家集団内のものになるのである.
20年後に, 応用生態工学はいかになっているか. いや, 土木工学や生態学はいかに変貌し, さらには解体してしまうのか. これはまことに楽しみなことである. ひょっとすると, 今まで生態学しかやってこなかった私自身も また, この応用生態工学研究会での討論・実践を通じて, 解体し変貌することができるかどうか. これを自分自身としても, 楽しみに見守りたい.

1)これは, 1997年10月15〜16日に東京のダイアモンド・ホテルで開かれた, 「応用生態工学研究会」の発足総会および研究発表会における, 川那部の挨拶および基調講演の内容を中心にして, それに大幅な加筆変更を加えたものである.
2) e-mail: kawanabe@lbm.go.jp


Copyright (C) 1999- Ecology and Civil Engineering Society
